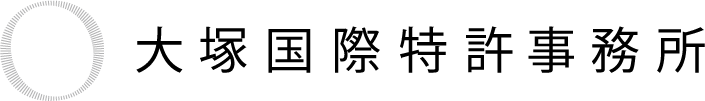この事件において、CAFCの大法廷は、PTOの拒絶の判断に対して、米国特許法第145条に基づく民事裁判によって地方裁判所に審理してもらう場合には、特許出願人が新たな証拠を提出する上で何ら制限を受けないと判決しました。これは、PTOの審判部の決定を不服としてCAFCへ控訴する場合に、FREおよびFRCPに基づきPTOの記録に縛られ、新たな証拠提出が制限されているのとは対照的です。この事件は、146条に基づき審判部へ審判を請求する手続きを経てCAFCへ控訴するよりも、145条に基づく民事裁判を選択する方が有利な場合があることを示しています。
CAFCは、米国特許法第145条に基づく民事訴訟において提出された新たな証拠を、地方裁判所が連邦証拠規則(以下、FRE)および連邦民事訴訟規則(以下、FRCP)に基づく民事訴訟においてのみ認められるものであることを理由に除外したことは、裁量権の乱用であったと認定した。したがって、CAFCは地方裁判所の判決を破棄し、意見書に同調し、さらなる審理のために事件を差し戻した。
この事件は、控訴ではなく、特許法第145条に基づく民事訴訟において新たな証拠を提示する出願人の権利に関するものであった。特許庁における審判手続とは対照的に、第145条の民事訴訟は、特許控訴抵触審判部(以下、審判部)の決定に不服な出願人に、米国特許商標庁(PTO)の手続きが終了した後で新たな証拠を提出する機会を与える。ある争点に関する新たな証拠を出願人が提出すると、地方裁判所はその争点を最初から審理し、審判部の決定には制約されない。
この事件において、出願人であるハイヤットは、117個のクレームを記載した特許出願を提出した。審査官は117個のクレームに対し、記載要件及び実施可能要件の違反、自明性型二重特許、新規性欠如、および自明性を理由とする2546個の拒絶を発行した。
ハイヤットは個々の拒絶理由に関して審判部に控訴した。審判部は記載要件以外の全ての審査官の拒絶理由を破棄した。ハイヤットは再審理の申請を提出したが、審判部は、ハイヤットが、審査官や審判部に対して以前に提示することが可能であった新たな議論を提起したと認定して、その実体を考慮することなく申請を却下した。
続いて、ハイヤットは、米国特許法第145条に基づき、コロンビア特別区合衆国地方裁判所に特許庁長官を相手とする民事訴訟を提起した。特許庁長官は、係属中のクレームが明細書記載要件を満たしていないとする略式判決の申し立てをした。
ハイヤットはその申し立てに対抗し、当業者であればクレームに対応する十分な記載が存在すると判断すると思われる明細書の部分を指摘した宣誓書を提出した。特許庁長官は、ハイヤットが以前に審査官や審判部に対してそのような宣誓書を提出しなかったことから、裁判所はその宣誓書を考慮すべきではない、と主張した。
地方裁判所は、ハイヤットがその宣誓書を以前に提出しなかったことに過失があると判断したが、その理由は、ハイヤットがそれ以前に審査官もしくは審判部に提出することが可能であった、記載要件の拒絶に関する宣誓書が提出されたからであった。
したがって、地方裁判所はその宣誓書を除外して、特許庁長官の主張を認める略式判決を下した。
ハイヤットは控訴したが、CAFCの合議体では意見が割れたものの、多数派は地方裁判所の判決を支持した。
CAFCは、出願人が審査官の拒絶理由に対する応答において、出願人が所有する証拠の提示を故意に拒否していたのであるから、地方裁判所がその宣誓書を除外したことは裁量権の乱用ではない、と判示した。それに対して、ハイヤットは、全員法廷での再審理を求めた。CAFCの全員法廷は、合議体の決定を破棄した。
全員法廷での再審理において、CAFCは、特許法第145条の手続きに対して適用可能な証拠能力の制限は、FREおよびFRCPによって制約を受ける制限であると判示した。第145条は、全ての民事訴訟に適用するFREとは別であり、独自の証拠規則はなく、地方裁判所に対して新しい証拠を提示する出願人の可能性を制限することを規制するものであり、第145条に基づく民事訴訟は、出願人が特許庁の記録に制限される審判手続きとは異なる、とCAFCは説明した。
CAFCは第145条の立法経緯とその前身の法律を審理したところ、議会は出願人が新たな証拠を自由に提示する民事訴訟を認めることを意図していた。
PTOの設立当時、議会は出願人の「エクイティ上の訴状による救済」を可能にする1836年法を制定し、明文化された仕組みはエクイティ裁判所における最初の裁判において開始された。
1927年、この手続きの提案者と反対者は、証拠が先の手続きにおいて特許庁に提出されているか否かにかかわらず、地方裁判所に新たな証拠を提示することを出願人に認めることに同意した。
後の特許法の改定において、議会は、第145条に基づく民事訴訟(実質的に「エクイティ上の訴状」手続きを残している)もしくは第146条に基づくCAFCへの控訴のどちらかを選ぶ権利を出願人に与えた。したがって、第146条に基づいてPTOとは反対の決定を求めて控訴することを選んだ出願人は、第145条に基づく手続きの権利を「放棄」するものである。
ゆえに、制定法の文言および長い立法経緯を考慮して、CAFCは、FREおよびFRCPの規則にだけ従った第145条の手続きにおいて、出願人が自由に新たな証拠を提示することを議会が意図していたと判断した。
CAFCは、新たな証拠は、出願人が正当な理由により審査期間中にPTOに提出できなかった場合のみ提示することができるというPTOの主張を拒絶した。
CAFCは、最高裁は一貫してそのような証拠は地方裁判所の手続きにおいて提出可能であると認識していると述べたが、また、地方裁判所にはこの証拠に重きを置くかどうかについての裁量があると述べた。
行政手続法(APA)に基づく事実認定に関する行政機関としてのPTOの主張について、CAFCは、もし誰も新たな証拠を提示しなければ、APA基準が適用されると説明した。しかしながら、新たな証拠が提示されたのであれば、地方裁判所は独自の事実認定を行うことができ、APAによって制限されることはない、と述べた。
反対意見は、多数意見の判示が、全ての民事裁判に適用される証拠の制限やFREおよびFRCPとは別に、出願人が地方裁判所に新たな証拠を提示する権利に制限を与えないことを強要するものであると指摘した。反対意見は、この判示は行政上の(救済)手段を尽くす要件を弱体化させるものであると主張した。
ハイヤット事件は、特許法第146条に基づき審判部の判決を不服としてCAFCへ控訴するのとは対照的に、第145条に基づく審理を求めた場合には、出願人がPTOの記録には制限されないことを明らかにした。したがって、特許出願人はPTOへの証拠提出を保留して、後に民事裁判において地方裁判所にそれを提出することを選択することが可能であろう。
Key Point?この事件において、CAFCの大法廷は、PTOの拒絶の判断に対して、米国特許法第145条に基づく民事裁判によって地方裁判所に審理してもらう場合には、特許出願人が新たな証拠を提出する上で何ら制限を受けないと判決した。これは、PTOの審判部の決定を不服としてCAFCへ控訴する場合に、FREおよびFRCPに基づきPTOの記録に縛られ、新たな証拠提出が制限されているのとは対照的である。この事件は、146条に基づき審判部へ審判を請求する手続きを経てCAFCへ控訴するよりも、145条に基づく民事裁判を選択する方が有利な場合があることを示した。