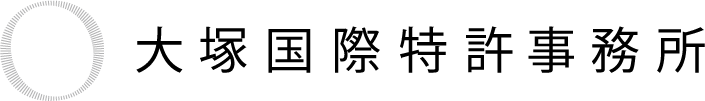この判決で最高裁は、姓名の商標登録を認めないLanham法2条(C)項はコモンローの伝統を受け継ぐものであり、言論の自由と共存関係にあるので違憲ではないと判断した。
姓名の商標登録を認めないランハム法の規定の合憲性が争われた事件
Steve Elster は、T-シャツや帽子に使用するマーク “Trump too small”を商標登録した。このマークは、2016年の共和党大統領候補であるトランプ候補とルビオ上院議員の討論会から着想を得たもので、トランプ氏の人柄と政策があまりにも矮小であるという政治的なメッセージが込められていた。
PTOは、生存する特定個人の名前から構成されるマークについては、本人の承諾がない限り商標登録は認められないとする「姓名規定」(商標法§1052(c))を根拠にElsterの商標出願を拒絶した。Elsterは拒絶を不服として審判を請求し、商標法の姓名規定が表現の自由を定める憲法第一修正に違反すると主張した。審判部は審査官の判断を支持し、拒絶査定が確定した。ElsterはCAFCに控訴した。CAFCは、姓名規定が憲法第一修正(「表現の自由」の保証)に違反すると判決し、PTOの拒絶査定を破棄した。PTOは連邦最高裁に上告した。
最高裁は、商標法の姓名規定が表現の自由に抵触しないと判決し、その理由を次のように述べた。これまで最高裁は、思想を表す表現や反道徳的な表現を規制する商標法の規定について違憲の判決を行ってきた。しかし、姓名に商標登録を認めないという方針は、コモンローの伝統であり姓名規定はそれに立脚して確立したものである。姓名規定は憲法第一修正と共存関係してきた歴史を持つ。姓名規定のこのような歴史と伝統は、それだけで表現の自由に違反しないということを立証するのに十分である。
反道徳やスキャンダラスな表現であることを理由とした商標登録の拒絶は視点に基づく差別(viewpoint-based discrimination)であるとして退けたのがMatal事件(2017年)とBrunetti事件(2019年)である。本件は「内容に基づく差別」(content-based discrimination)を争うものであり、これまでの判例とは異なる。