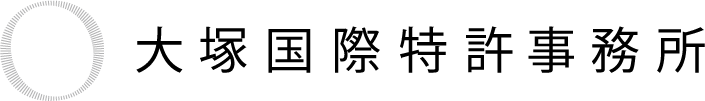この判決において、CAFCは、既決のIPR手続きで主張可能だったにもかかわらず主張しなかった理由をベースに新たなIPR手続きを求めることを禁止した。
既決のIPR手続きで主張可能だったにもかかわらず主張しなかった理由をベースに新たなIPR手続きを求めることを禁止したCAFC判決
既決のIPR手続きで主張可能だったにもかかわらず主張しなかった理由をベースに新たなIPR手続きを求めることを禁止したCAFC判決を紹介する。
米国特許庁の審判部で行われるIPRの最終決定が下されると、IPRの申請者はそのIPRの手続きで主張した、または主張することが可能であった無効理由を、新たなIPRで主張することを特許法Section 315(e)は禁止している(禁反言)。
ところが、“主張した、または主張することが可能であった”(raised or reasonably could have raised)の文言が具体的にどのような意味なのかについて異なる解釈があった。CAFCはShaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016) (Shaw事件)で “raised or reasonably could have raised”とは、PTABが、IPRを受けて審理を開始(Instituted)させた理由を意味し、主張したもののPTABが受け入れなかった理由は禁反言の対象ではないと説明した。しかし、決定が出ているIPR手続きの中で主張可能であったが主張しなかった理由に関しては触れていなかった。
したがって、“raised or reasonably could have raised”は、主張しなかった理由を含む、或いは、含まない、と解釈が割れていた。
今回のCaltech v. Broadcomでは、主張することができた全ての理由を禁反言の対象に含めるように、特許法315条(e)を解釈した。
なお、2月4日に出された判決は、2月22日に判決の訂正が発表され、禁反言は請求項ごとに適用されることが明瞭になった。例えば、あるIPRで請求項1に対する無効を主張したとしたら、申請者はその請求項に対して主張することが可能であった他の無効理由はすべて主張できなくなる。しかし、請求項1以外の請求項に関して禁反言は適用されない。
何れにしてもしっかりとした準備で、IPRを請求しないと、手持ちの証拠の活用が制限されることに注意しなければならない。
情報元:
Dr. Min Woo Park
Morgan, Lewis & Bockius LLP