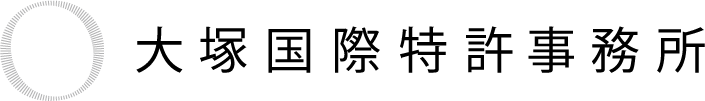この事件では、自明性型の二重特許に対して、1方向テストもしくは2方向テストのいずれかが適用され、2方向テスト(ミラーイメージ)は審査過程における遅延に対し特許庁が責任を有するときにのみ採用される例外であることが明らかとなりました。また、自明性型の二重特許の分析においては、必ずしも、Grahamによる自明性の分析は必要とされないことも明らかになりました。
自明性型のダブルパテントを判断するための2つのテスト
CAFCは、ナッタ社(Natta)の米国特許第6,365,687号(687特許)のクレームが自明性型の二重特許論のもと認められないとした特許抵触審判部(以下、BPAI)の審決を支持した。
687特許は、触媒の下で実行される不飽和炭化水素の重合に関するものである。687特許の係属中のクレームは、チタニウムハロゲン化合物アルミニウムアルキル触媒を使用することを特定している。
2002年4月2日に687特許が発行された後、特許庁は2002年6月7日に長官の命令による再審査を開始した。再審査の根拠は、米国特許第3,582,987号(987特許)をはじめとしたナッタ社により所有されていたものの、既に失効したいくつかの特許に対する自明性型の二重特許である。
Eli Lilly & Co. 対 Barr Labs., Inc.事件(注1)での判決が示すように、自明性型の二重特許論では「同一人が所有している先の特許のクレームと、特許的に区別できない後の特許のクレーム」は無効とされる(注2)。
二重特許の決定に際し、CAFCは「1方向」テストもしくは「2方向」テストのいずれかを用いる。1方向テストでは、「審査官は出願中のクレームが特許クレームに対して自明性を有するかを問う」(注3)。
2方向テストでは、「審査官はまた、特許クレームが出願中のクレームに対して自明性を有するかも問う」(注4)。
CAFCは、1方向テストは通常採用されるテストであり、2方向テストは「第1の出願の前に第2の出願が発行されることになった遅延について、特許庁が単独で責任を有する」(注5)場合に採用される限定的な例外であると説明した。
CAFCは2方向テストでなく1方向テストを選択したことにおいてBPAIを支持した。
CAFCは、「特許権者は、他の発明をカバーしているクレームに関係したクレームを繰り返し提出し、関係のない発明に対して審査官に抵触審査の宣言をさせ、しかも審判請求をすることなく繰り返し継続出願を実行した」(注6)と述べた。
故にナッタ社はその行動と怠惰を通して手続きを遅延させた責任があり、したがって1方向テストが適用可能であると結論づけた。
ベセル社(Basell)は、687特許の審査手続き中に、既に審査官が987特許を検討していたと述べた。故に、法改正前の米国特許法第303条(a)及び In re Portola Packaging, Inc.(注7)並びに In re Recreative Technologies Corp.事件(注8)でのCAFCの判決に従い、987特許は再審査において考慮される必要がないと主張した。
CAFCは、987特許は687特許の審査過程において検討されておらず、むしろ同じパテントファミリーに属する別の出願である米国特許出願番号06/498,699号(699出願)において検討されていることを指摘した。
687特許は1983年に出願された699出願の4代目にあたる出願から発行されている。しかしながら、CAFCは699出願の審査過程における987特許の検討は、争点となっている687特許のクレームとは異なるクレームに関するものであったと認定した。
故に、CAFCは、Portola もしくは Recreative Technologies 事件のもとの検討から987特許は排除されないと結論づけた。
CAFCはさらに、自明性型の二重特許による拒絶は米国特許法第103条における自明性の分析と必ずしも同じではないが、類似するものであると説明した。
特に、CAFCは、BPAI が Graham 対 John Deere Co.事件(注9)に準じる十分な自明性の分析を行わなかったことは、自明性に関するBPAIの決定を覆す理由とはならないとした。
CAFCは、687特許のクレームにおける限定要素は、987特許のクレームを自明の範囲内で変形した限定要素に過ぎないと結論づけた。
特に、CAFCは、両方のクレームセットがチタニウムハロゲン化合物とアルミニウムアルキルの触媒を使用したオレフィンとの重合における様々な変化に関するものであり、その表現のなかのいくつかは残りのものに対してジェネリックなものであったことに注目した。
CAFCは、ジェネリックな表現はそれを包含するすべての種に対して自明性を持たないとされるわけではないことを認識していた。それにもかかわらず、この特定の事件においては、両方のクレームセットは、「同じ種のグループに関係し、互いに置換できる方法で互いにジェネリックであり、特有でもあった。」(注10)。
結果として、CAFCは687特許のクレームは自明性型の二重特許により無効であると判断した。
CAFCは、687特許の二重特許を調査する中で987特許の開示が使用されているという問題を審理し、二重特許の調査において特許の開示を先行技術として用いることはできないという命題のために、In re Kaplan(注11)を引用した。
同時に、CAFCは、他の状況においては特許の開示を用いることできるという命題のために、In re Vogel(注12)をあらためて支持した。
発明の開示は「出願に係るクレームが特許でクレームされた発明の単なる自明な変形かどうかを決定する」(注13)ために用いられ、文言の意味を理解するために用いられ、さらに「クレームの技術的範囲を解釈する」(注14)ためにも用いられる。
CAFCは、BPAIが987特許の明細書を参照したことは、クレームが987特許のクレームと特許的に区別できるかどうかを決定するために限定されていたために、不適当ではなかったと判断した。
この事件は、自明性型の二重特許に対し、1方向及び2方向テストの適用性を明らかにしたため、重要である。特に、1方向テストは通常のテストであり、2方向テストは特許庁が審査過程における遅延に責任があるときにのみ採用される。この事件はまた、自明性型の二重特許において特許が無効であるかどうかを決定するためには、Grahamによる十分な自明性の分析は必ずしも必要ではないことを明らかにした。