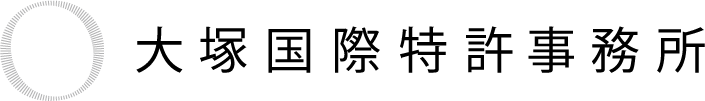この報告では、アルナイラム・ファーマシューティカルズ社(Alnylam Pharmaceuticals, Inc.)が、モデルナ他2社をUSP11,246,933号及び11,382,97号に基づいて訴えた特許権侵害事件の争点となった、明細書中に記載された定義に基づくクレーム解釈の問題を取り上げる。
明細書中に記載された定義に基づくクレーム解釈の可否が争われた事件
特許出願を作成する際、発明者は特許法35 U.S.C. §112(b)の下、発明者等が自らの発明と考える発明の主題を特定して明確に特許を請求する一つまたはそれ以上の請求項を含めなければならない。請求項では、用いる用語が広範な意味を持ち、十分に明確であるべきかを慎重に吟味しなければならない。
さらに、急速に進化する先端技術分野を扱う場合、発明者が明細書中の用語を工夫して使用することもある。特許権者は「自ら用語の定義者(lexicographer)となり、一般的な意味とは異なる意味で用語を使用することができるが、その定義は明細書またはファイル履歴に明確に記載されていなければならない」ことは広く理解されている(Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996)、Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd., 78 F.3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1996))。実際、多くの特許明細書には「定義(Definitions)」の見出しの下に、明細書および請求項が使用する用語の具体的な定義が記載されている。
米国特許実務におけるもう一つのよく知られた原則は、「明細書に記載された限定を請求項に読み込むことは原則として適切でない」ということである。言い換えれば、請求項中に明示的に記載されていない限定を、明細書を根拠として請求項に追加して解釈することは通常認められない。明細書の役割は、請求項に対する文脈と支持を提供することであり、請求項の文言から読み取れる範囲を超えてその範囲を狭めることはできない。
しかし、これら二つの原則が、請求項中の用語の意味解釈において、しばしば困難を引き起こすことがある。まさにこの点が争点となったのが、2025年6月4日にCAFCで判決が下されたAlnylam Pharmaceuticals, Inc対Moderna, Inc 事件である。
米国特許第11,246,933号は、カチオン性脂質に関するもので、その脂質性部分(例:疎水性鎖)に一つ以上の生分解性基を含む構成となっている。「定義」の項では、以下のように記載している:
特に断らない限り、「分岐アルキル」、「分岐アルケニル」、「分岐アルキニル」という用語は、アルキル、アルケニル、またはアルキニル基において、1つの炭素原子が(1)他の炭素原子3つ以上と結合し、かつ(2)環状基の環原子ではないものを指す。例えば、アルキル、アルケニル、アルキニル基中のスピロ環状基は、分岐の点とは見なされない。
請求項18は、以下のように定義している。
「カチオン性脂質であって、第一の基と、二つの生分解性疎水性鎖を含み、少なくとも一つの疎水性鎖の末端にある疎水性鎖が分岐アルキルであり、該分岐は生分解性基に対してα位に存在し、疎水性鎖は-R12-M1-R13の構造を有し、ここでR12はC4〜C14アルキレンまたはC4〜C14アルケニレン、M1は生分解性基、R13は分岐C10〜C20アルキルであり、R12-M1-R13の合計炭素数は21〜26である…」
当事者間では、クレームが前述の定義に限定されるのであれば、被告Modernaの製品は「他の炭素原子3つ以上に結合した炭素原子」を有さず、特許を侵害しないことに争いはなかった。地方裁判所は、請求項は明細書中の定義に従って限定されると判断し、Modernaによる侵害はないとの判決を下した。
控訴審において、CAFCは、地方裁判所のクレーム解釈を独自に検討し、明細書などの内在的証拠のみに基づいて適切にクレームを解釈して、地方裁判所のクレーム解釈及び判決を支持した。
この判決は、請求項中の用語を明細書の定義に基づいて限定すべきか否かを判断する際に、裁判所が考慮すべき要素について示唆に富んでいる。
本判決はまず、「内在的証拠は、請求項の用語を明確に定義するか、または明確に再定義するものでなければならず、それによって当業者がその用語の再定義を出願人が意図していることを認識できるようにしなければならない」と述べた(Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Group, Inc., 262 F.3d 1258, 1268 (Fed. Cir. 2001) を引用)。裁判所は、明細書中の用語を「内在的証拠」として指しているようである。続いて裁判所はいくつかの要素について議論した。
第一:問題となる記載が「Definitions(定義)」という見出しの下に記載されていたこと。この点について、過去の裁判例において、「以下に定義する(defined below)」という表現が用いられていた場合、拘束力のある定義と認めた例があると述べている。
第二:定義される用語「branched alkyl(分岐アルキル)」が引用符で囲まれていること。これは通常、続く文が定義である強い示唆である。
第三:問題となる記載が「refer to(〜を指す)」という表現を用いていること。これは続くセンテンスが定義を意図していることを示す。
第四:同じ「Definitions」項で、Alnylamが、問題となる「refer to(〜を指す)」で始まる記載とは対照的に非限定的な表現を使っていること。「for example(例えば)」「non-limiting examples(限定されない例)」「include(含む)」「include, but are not limited to(含むがこれに限定されない)」といった用語で始まる記載が他にある。
第五:問題となる記載に「特に断らない限り(unless otherwise specified)」という文言が含まれていること。これは、続くセンテンスが一般的に適用されるルールまたは定義であることを示している。
裁判所は、これらの要素を総合的に判断し、問題となる記載は定義であると認定し、したがって請求項中の該当用語の意味を限定すべきであると結論づけた。さらに裁判所は、「特許において、lexicography(特定の定義)が成立するためには高い基準が必要であるのと同様に、その定義から逸脱するには同様に高い基準が必要である」と述べ、この事案ではそのような逸脱は認められないと判断した。
判決は、続いて化学構造に関する技術的分析を詳細に行い、明細書全体の技術的記載が、定義に従った請求項解釈と整合していると結論づけた。ただしこの部分は一般的な指針を示すうえでは有用ではないため、ここでは省略する。
このように、明細書中の定義は、明確性を確保するうえで有用であり、場合によっては不可欠であることもある。しかし、発明者は、それが請求項を限定的に解釈する影響をもつことを十分に留意し、上記に示された各要素に注意を払う必要がある。
報告者紹介
William C. Rowland
Shareholder, Buchanan Ingersoll & Rooney
William C. Rowland is co-chair of Buchanan’s Intellectual Property section and Patent Prosecution group, and is the Mechanical Practice Group leader. His practice is focused on client counseling on intellectual property matters, concerning both domestic and international issues, as well as drafting and prosecuting patent applications in mechanical, optical and electrical technologies and industrial designs.
He earned his J.D. from The George Washington University Law School in 1980, following his B.S. in Mechanical Engineering from the University of Vermont, where he graduated cum laude in 1977.
弁理士 木下智文
大塚国際特許事務所 弁理士
東京大学大学院・薬学系研究科・分子薬学専攻・修士課程修了。薬剤師。日本弁理士会国際活動センター米州部部長、同部研究成果報告セミナー講師、同副センター長、同会常議員を歴任。大塚国際特許事務所のシステムアドミニストレータとしても活躍する。医薬、化学、ネットワーク、画像処理の特許、訴訟を得意とする。