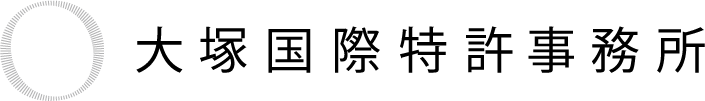審査の段階では、102条の法定の要件に関わらず、出願人が公知と自認した技術は先行技術となり、これを基に新規性や自明性を否定できる。ところが、この自認による先行技術は特許法311条(b)が規定する公知例には該当せず、IPRの証拠資料にはならないとした。
Qualcomm は、異なる供給電圧で作動するシステム用の電力検知半導体に関するUSP 8,063,674を保有する。Appleは、この特許の複数のクレームが自明であるとして2件のIPRを申請した。最初のIPRでは、先行特許(Steinacker、Doyle及びPark)を無効資料とし、2つ目のIPRでは、明細書中の従来技術の記載において出願人が自認した公知技術(applicant admitted prior art ‘AAPA’)と出願公開中の技術の組み合わせを無効資料とした。
Qualcommは、特許法311条(b)によりIPRの根拠として認められる無効資料は、102条の要件を満足する先行特許と刊行物だけであるとして、AAPAには証拠適格がないと主張した。しかし、PTABは、出願人が自認した公知例も311条(b)で定める公知例に該当するとして、AAPAの証拠資料が適正であると決定した。この決定を不服としてQualcommはCAFCに控訴した。
CAFCは、PTABの決定を破棄し、事案をPTABに差し戻した。その理由を次のように説明した。本件の問題は、AAPAが「特許と刊行物からなる公知例」(311条(b))に該当するか、IPRの無効資料となりうるか否かである。CAFCは、該当しないと考える。この解釈は、最高裁判例(Return Mail, Inc. v. U.S. Postal Serv., 2019) およびCAFC判例(Regents of the Univ. of Minn. v. LSI Corp., 2019)に沿うものである。
なお、この判決より前の、2020年8月18日に米国特許庁のAndrei Iancuは、IPRでの無効資料の証拠適格性に関し、次のようなメモランダムを発表した。
IPRを審理するPTAB(特許審判部)の多数意見は、AAPAだけではIPRの請求を認めていない。しかし、Apple v Qualcomm(IPR2018-01315)、Intel v IP Bridge (IPR2018-00951)などでは、AAPAと他の先行特許、刊行物との組み合わせを認めていた。そこで、PTABの見解の統一をはかるため、IPRで認められる先行技術は、特許、刊行物に限られること。そして、IPRで争われるその特許の明細書の記載(即ち、自認による先行技術は)、そのIPR手続での先行技術にならない。
ただし、AAPAは311条下では使用できなくても、IPRに使用できないという訳ではない。その他の目的―例えば、証拠を補強する宣誓供述書(312条)、PTO長官あての情報提供(314条)、IPR申請後の追加情報の提供(316条)などに使用できる。