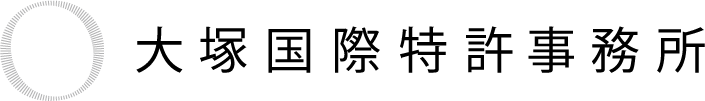この事件では、損害賠償の認定の基礎として陪審が採用できるような実質的な証拠をルーセント・テクノロジーが提出できなかったため、CAFCは、マイクロソフト・コーポレイションに対する損害賠償を認める地裁判決を破棄しました。このような判断が認められる範囲を限定するために、CAFCは、損害額決定のための全体市場価値ルールの継続的な有効性を支持しました。
製品の一部機能が特許権の侵害を構成する場合および同様のライセンス契約が存在する場合における損害賠償額の算定方法
この事件で、CAFCは、被告マイクロソフト(Microsoft Corporation)から原告ルーセント(Lucent Technologies, Inc)への約3億5800万ドルの陪審員の裁定を破棄した。
また、CAFCは、特許の有効性及びマイクロソフトによる侵害に関してマイクロソフトが行ったトライアル後の申し立てについての却下を支持した。
争点の米国特許第4,763,356号(以下、デイ特許)は、キーボードを使わずにコンピュータ・スクリーン上のフィールドにデータを入力する方法を対象とする。
ユーザは、フィールドと同時に表示される、予め定義された入力支援ツールを選ぶことによって、表示されたフィールドに記入する。このようなツールはスクリーン上のグラフィカル・キーボード、メニュー、及び計算機を含む。
審理において、陪審員は、特許が有効であり、マイクロソフト・アウトルック、マイクロソフト・マネー、及びウィンドウズ・モバイルの販売を通じてマイクロソフトにより特許権が間接侵害されていると認め、この三つのソフトウェア製品の販売に対して総額3億5千万ドル強の損害賠償額を一時金として支払うよう裁定した。
まず、CAFCは、デイ特許のクレーム19及び21は米国特許法第103条のもと自明であるから無効であるという、マイクロソフトによる法律問題としての判決を求める申し立てについて地方裁判所が却下したことを支持した。地方裁判所が認定していたように、ルーセントに最も有利な視点では、技術が出願時点で自明ではないという陪審の認定を支持した。
間接侵害を否認するマイクロソフトの主張は、(1)ルーセントが間接侵害の認定に対して必要な証明を提出できなかったこと、(2)実質的な非侵害の用途が存在するため、ルーセントは寄与侵害を証明できなかったこと、(3)責任を負うべき侵害誘発の意図をマイクロソフトが有していることをルーセントが証明できなかったことを含む。CAFCはこれに同意しなかった。
CAFCは、直接侵害の直接的な証拠はほとんど存在しないものの、直接侵害の十分な状況証拠が存在すると認定した。
ルーセントの専門家は、マイクロソフトが訴えられた日取り選定ツールを設計しただけでなく顧客に対してそれを使用するように指示したと証言した。この証言及びマイクロソフトの販売の証拠に基づいて、陪審は2003年から2006年の間に恐らくは少なくとも1人がツールを使用したと認定した。
寄与侵害の争点は、米国特許法第271条(c)の「物質または装置」の境界を裁判所がどのように設定したかに帰着した。
マイクロソフトは、物質または装置とは多くの実質的な非侵害の用途を有するプログラムであるマイクロソフト・アウトルックであると主張した。しかしながら、ルーセントは、物質または装置とは日取り選定ツールであり、実質的な非侵害用途を有しないと主張した。
地方裁判所はルーセントに同意し、法上の物質または装置とはツールであってプログラムではないとした。マイクロソフトの主張を採用してしまうと、不当な状況を作り得ると論理付けした。例えば、被告は機能がより大きなプログラムに別々に組み込むことによって法的責任を回避しうるだろうというとの考えがそこにはある。
誘発について、CAFCは、ルーセントが必須の意図を示すことが出来なかったというマイクロソフトの主張を却下した。ルーセントの専門家は、ユーザはマイクロソフト・アウトルックを使用しつつ侵害ツールの使用を回避することは出来ないだろうと証言した。また、マイクロソフト自身の文書が侵害対象ツールの使用をユーザに促していると言及した。この証拠に基づいて、陪審の認定は十分に根拠を示していた。
CAFCはその後に損害賠償を検討した。逸失利益は争点でないため、地方裁判所は、陪審の賠償を支持する実質的な証拠が存在するかどうかを確認するために、良く知られたジョージア・パシフィック・フレームワークのもとで分析を実行した。Georgia-Pacific Corp.対 U.S. Plywood Corp.事件、318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y 1970)参照。
争点は、陪審による約3億5800万ドルの一時金の損害賠償が実質的な証拠によって裏付けられるかであった。争点の核心は、ルーセントが一時金の賠償を考えておらず、ランニング・ロイヤリティを考えており、それに相当した証拠を提示した点である。
特に仮想的な交渉の状況においては、一時金のライセンス合意とランニング・ロイヤリティのライセンス合意との間に差異があるため、評決が実質的な出発点となった。
CAFCによれば、一時金で特許権をライセンスすることによって、特許保有者は相当な一時金を得る一方、ライセンシーは支払いの上限を定めることができる。さらに、両者ともに、ランニング・ロイヤリティの計上といった管理コストの負担から解放される。これらの利点は双方が負うリスクによって均衡が保たれる。
ライセンサーは、ライセンスした製品が予想よりもはるかに成功するリスクを抱える。ライセンシーは、ライセンスされた製品が予想したほど成功しないリスクを抱え、一時金の支払いから損失を抱えるかもしれない。
販売が予想できない方向に進行した場合に、どちらの当事者も後戻りできない。これらのリスクのため、当事者は、ライセンス付与の時点で、特許発明の予想される用途の合意を得る必要がある。
予想される用途が広ければ要求される額は高くなるだろうし、その逆も成り立つだろう。陪審が一時金による賠償額を裁定するためには、これらの予想の実質的な証拠と、賠償額が単なる推測であるというその他のリスクの実質的な証拠を有していなければならない。
CAFCは陪審による一時金での賠償について三つの主な争点を審理した。第一に、どれくらいの頻度で特許方法が顧客によって使用されるかについての当事者の予測を証拠によっては確立できていなかった。
第二に、陪審では、合理的なロイヤリティに対して向けられたライセンスの合意が一時金の支払いを決定するためにどのように用いられるかについての証言がほとんど得られなかった。
第三に、ルーセントが頼った証拠によれば、本件の特許権の侵害を回避するためのライセンス交渉からはるかに離れた状況においてライセンスが成立した。
裁判所によれば、当事者の予測であるという証拠の欠如に加えて、当事者同士によるライセンスは不十分であった。ルーセントは、ライセンス合意に基づいてそれがどのように一時金の賠償に到達しえるかを陪審に示していなかった。四つの一時金の合意のうち、三つによってカバーされる主題または特許に関する専門家の証言は提供されていなかった。
第四としては、IBMの全特許ポートフォリオをDellにライセンス付与する合意であり、これは全く異なると裁判所は認定した。
ランニング・ロイヤリティの合意はCAFCの分析のもとでも、同じような結果であった。ルーセントは、ランニング・ロイヤリティの合意が一時金の損害賠償額を算定するための基礎としてどのように役立つかを陪審に示さず、また、合意に至ることに関する要因と合理的なロイヤリティの交渉における要因との間の違いがどのように損害賠償額に影響するを陪審に説明できなかった。
これらの違いは、(1)技術における差異、(2)ライセンスが製品全体をカバーするか一部をカバーするか、(3)ライセンスされた特許権の数、(4)特許発明の価値、(5)特許製品の販売価格、(6)クロスライセンスの効果、を含む。
どのように行われるかが示されることがなったため、陪審がこれらの合意を合理的な一時金の賠償額を算出するために用いることはできなかったと思われる。
裁判所はその後に賠償の総額が合理的かどうかに着目した。裁判所は、日取り選定ツールはソフトウェアの大部分と比較して極めて微小な機能に過ぎないと認定した。そのようなものとして、当事者がこの機能をソフトウェアの販売価格の約8%であると評価することはないだろう。
また、裁判所は侵害製品が顧客により実際に使用されることはほとんどないと言及した。
ルーセントは、3本のソフトウェアがこれらの形式の多くを含み、実質的に侵害する使用を暗示していると主張した。しかし、裁判所はこの主張は侵害する使用に焦点を当てておらず、侵害者が非侵害機能を使用したという証拠による損害賠償を支持できていないと判断した。
CAFCはこの認定と間接侵害の認定とを区別した。陪審による間接侵害の認定を支持するのに十分な状況証拠はあるものの、それは単に少なくとも1人がアメリカ合衆国において関連する期間内のいつかの時点で特許方法を実行したという暗示的な認定を裏付けるだけである。従って、ルーセントは侵害方法の使用範囲が一時金の賠償を支持するということを証明する責務を果たせていなかった。
提出された証拠が実質的な証拠として採用されるための閾値まで届かないため、裁判所は賠償額が憶測や推量に基づいており、審理を維持できず、よって、損害に関する新たな審理が必要であると判断した。
裁判所は、証拠におけるライセンスが法律問題として不十分というわけではなく、提出された証拠が「実質的な証拠」に達していないことを明確にした。
CAFCはその後にエンタイヤーマーケットバリューに関するマイクロソフトの主張を検討した。このルールにより、いくつかの機能を含む装置全体のエンタイヤーマーケットバリュー(全市場価値)に基づいて損害の回復を可能とする。
しかし、裁判所は特許関連機能が顧客の需要の「基礎」をなす場合にのみこのルールは適切であると指摘した。裁判所は、日取り選定ツールがアウトルックの顧客需要の基礎をなすことを証拠が示していないと認定した。このようなものとして、エンタイヤーマーケットバリューは本事件では適切でなかった。
裁判所はその後にエンタイヤーマーケットバリューの種々の要件を検討し、特許ライセンスの複雑性の観点から、具体的には侵害部分に対する市場価値が確立されていない場面においてルールを擁護した。
裁判所はまた、すべての賠償が二つの部分、すなわちロイヤリティ・ベースとロイヤリティ・レートに基づくと説明した。ロイヤリティ・レートが侵害部分または侵害機能により表される全体との比率に対応する限りにおいて、ロイヤリティ・ベースとして製品価格を用いることは本質的に悪いことではないと裁判所は説明した。
事実上、ルーセントについての裁判所の認定は、損害賠償を請求する全ての特許保有者に関連する。この事件は損害の構造及び額の両方を証明する特許権者の責務に焦点を当てている。
特許権者が損害を証明するために同様のライセンス合意を根拠とする場合には、その類似点及び相違点が合理的なロイヤリティ賠償にどのように影響すべきかについて陪審を訓練しなければならない。